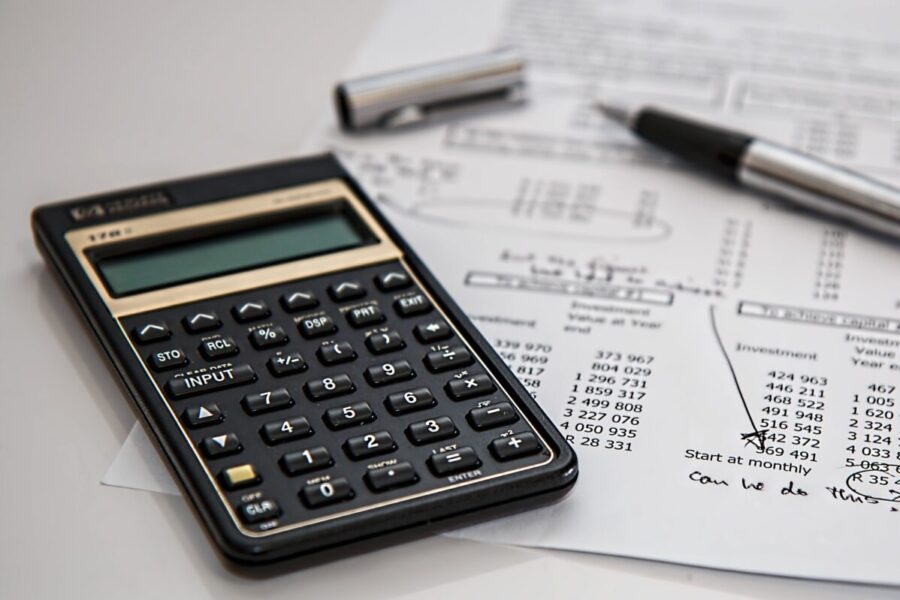リノベーションで抜けない柱の活用法とは?事例と注意点を解説

こんにちは!クジラ株式会社の菅原です!
 | Writer 菅原沙絵 デザイナー WORKS 2017年に新卒入社以来、住宅だけではなく店舗や宿泊施設のデザインも担当してきた。 お客様の理想を正確に捉え、ヒアリングを中心にデザインしていくことを得意としているデザイナー。 CREATOR’s STORY|菅原 沙絵 |
|---|
リフォームやリノベーションを検討する際、理想の間取りを実現したいと考える方は多いでしょう。しかし、建物の構造によっては撤去できない柱が存在します。これらの「抜けない柱」は、時にリノベーションの制約となることもありますが、実は工夫次第でおしゃれな空間を創り出す要素にもなり得ます。
本記事では、抜ける柱と抜けない柱の見分け方から、抜けない柱を活用する具体的なアイデア、さらにマンションにおける注意点やリノベーション事例、そして計画を進める上でのポイントまで詳しく解説します。
目次
抜ける柱と抜けない柱の見分け方

リノベーションで間取り変更を考える際に重要となるのが、既存の柱が撤去可能かどうかを見分けることです。日本の木造住宅で多く採用されている木造軸組工法では、柱が建物の構造を支える上で異なる役割を担っています。そのため、安易に柱を撤去すると建物の強度や耐震性に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
抜ける柱と抜けない柱の特徴を理解することで、より現実的なリノベーション計画を立てられるでしょう。
抜ける柱とは
リフォーム時に撤去が可能な柱としては、「間柱」や一部の「管柱」が挙げられます。間柱は主に壁の下地材を固定するために設けられる柱で、建物の構造そのものを支える役割は持っていません。そのため、壁を撤去する際には間柱も一緒に撤去できる場合が多いです。間柱は比較的細い木材が使用されており、壁の内部に等間隔で配置されています。
また、管柱の一部も、梁などで補強することで撤去できるケースがありますが、全ての管柱が撤去できるわけではありません。
抜けない柱とは
一方、リノベーションにおいて原則として撤去できない柱は、「通し柱」や構造上重要な「管柱」です。通し柱は、2階建て以上の建物で土台から軒まで一本で通っている柱であり、建物の構造を一体化させ、高い耐震性を確保する上で非常に重要な役割を果たしています。主に建物の四隅に配置されることが多いですが、他の位置にある場合もあります。これらの柱を抜いてしまうと、建物の強度が著しく低下し、安全性が損なわれるため、基本的に撤去は不可能です。
また、床や壁などを支える多くの管柱も、建物の構造を支える重要な要素であるため、抜けない柱に含まれます。
筋交いや壁、梁の注意点

リノベーションで間取り変更を行う際には、柱だけでなく、筋交いや壁、梁といった構造部材にも注意が必要です。特に筋交いは、柱と梁で構成される四角い枠の中に斜めに入れられる補強材で、地震などの横からの力に対する建物の耐震性を高める重要な役割を担っています。建築基準法でも一定の割合で筋交いを設けることが定められており、これを撤去すると耐震性が大幅に低下する可能性があるため、原則として抜くことはできません。
また、ツーバイフォー工法や壁式構造のような建物では、壁そのものが建物の構造を支える「構造壁(耐力壁)」となっている場合が多く、これらの壁も撤去はできません。構造壁は建物の強度や耐久性を保つために不可欠であり、撤去すると安全性が損なわれます。
さらに、梁も建物の荷重を支える重要な部材であり、安易に撤去したり位置を変更したりすることはできません。リノベーションでこれらの構造部材に手を加える場合は、建物の構造を熟知した専門家による詳細な診断と適切な補強計画が不可欠となります。
マンションの場合の注意点
マンションのリノベーションにおいては、柱や梁が建物の共用部分にあたるため、基本的に撤去や移動はできません。マンションの多くは鉄筋コンクリート造(RC造)で、柱や梁が建物を支える主要な構造体となっているためです。リフォームで間取りを変更したい場合でも、これらの構造体はそのまま残す必要があります。
また、マンションでは管理規約によってリノベーションの範囲や内容に制限が設けられていることが一般的です。事前に管理規約を確認し、どこまでリノベーションが可能か、どのような工事が制限されているかを把握しておくことが非常に重要です。
抜けない柱や梁がある場合でも、それらを活かしたデザインや家具の配置などを検討することで、魅力的な空間を創り出すことが可能です。
リノベーションで抜けない柱を活用するアイデア

リノベーションで抜けない柱があっても、それをマイナスと捉える必要はありません。むしろ、柱を空間デザインの一部として積極的に取り入れることで、個性的でおしゃれな空間を創り出すことが可能です。柱の存在を活かすアイデアは多岐にわたり、機能性とデザイン性を両立させることができます。ここからは、抜けない柱を活用する具体的なアイデアをご紹介します。
見せる柱で空間を演出する
抜けない柱をあえて隠さずに「見せる柱」として活用することで、空間のアクセントにすることができます。柱に異なる色や素材のクロスやタイル、塗装などを施すことで、周囲の壁とは異なる印象を与え、空間のフォーカルポイントとして際立たせることが可能です。例えば、白を基調としたシンプルな空間に、黒やダークブラウンに色付けされた柱があると、空間全体が引き締まり、モダンでスタイリッシュな雰囲気を演出できます。
また、木目の美しさを活かしたり、レンガや金属などの素材を取り入れたりすることで、温かみのある空間やインダストリアルな雰囲気など、様々なインテリアテイストに合わせることができます。
柱を活かした造作家具や棚の設置
抜けない柱の周囲に造作家具や棚を設置することで、デッドスペースを有効活用し、収納スペースを確保することができます。柱と柱の間や、柱と壁の間に棚板を設ければ、本棚や飾り棚として活用できます。観葉植物や小物などを飾ることで、空間のインテリア性を高めることも可能です。
また、部屋の中央にある柱を活かして収納棚を設置することで、空間をゆるやかに間仕切る役割も持たせられます。キッチンカウンターの一部として柱を活用し、飾り棚やニッチを設ける事例もあります。柱の形状や位置に合わせて柔軟にデザインできる造作家具は、空間に一体感を生み出し、機能的でおしゃれな空間を実現します。
間仕切りとしての柱の利用
抜けない柱を完全に壁で覆ってしまうのではなく、柱をそのまま見せる形で間仕切りとして活用する方法もあります。柱と柱の間に壁を設けずにオープンな状態にすることで、空間を完全に区切るのではなく、ゆるやかにゾーニングすることができます。これにより、視線が抜け、圧迫感を軽減しながらも、それぞれの空間の独立性を保つことが可能です。
例えば、リビングとダイニングの間に柱がある場合、その柱を活かして空間を区切ることで、それぞれの空間の雰囲気を保ちつつ、繋がりも感じられるようにデザインできます。格子状のデザインを取り入れることで、さらに抜け感やデザイン性を高めることも可能です。
ハンモックやキャットウォークへの活用
構造的にしっかりとした抜けない柱は、ハンモックやキャットウォークの設置場所としても活用できます。特に通し柱のように建物を強く支えている柱は十分な強度があるため、ハンモックを取り付けてくつろぎの空間を作ったり、猫の遊び場としてキャットウォークやキャットタワーを設置したりすることが可能です。
柱にビスを固定するだけで比較的簡単に設置できるため、リノベーションのアクセントとして取り入れやすいアイデアと言えます。ペットとの暮らしをより豊かにするだけでなく、遊び心のある個性的な空間を演出できます。
ただし、設置する際には柱の強度をしっかりと確認し、必要に応じて補強を行うことが安全のためにも重要です。
柱を使ったマンションリノベーション事例
マンションリノベーションでは、構造上抜けない柱が多く存在しますが、これらの柱を活かした魅力的な空間づくりが数多く実現されています。
キャットウォークの補強や爪研ぎに

リビングダイニングと廊下の動線になる、少し不便な場所にある柱。しかし、愛猫のキャットウォークを設置することになり、キャットウォークを補強したり、麻紐を巻きつけることで爪研ぎとしても活用できる柱になりました。リノベーションの際にしっかりプランを考えることで、邪魔になりがちな柱も上手く利用することができます。
天井や床と素材を合わせて馴染ませる

間口の狭い長屋では、階段を壁で覆わないことで部屋を広く見せることができます。柱が一本残っていても床や天井と素材を合わせることで、デザイン的にも違和感なく残すことができます。
リノベーション時の注意点とポイント

リフォームやリノベーションを成功させるためには、抜けない柱の存在を理解し、適切に対応することが重要です。事前の確認から計画、そして施工に至るまで、いくつかの注意点と押さえておきたいポイントがあります。
活用計画の前に確認すべきこと
抜けない柱を活かしたリフォーム計画を進める前に、まず確認すべきことは、どの柱が構造上撤去できない柱なのかを正確に把握することです。建物の竣工図を確認することで、ある程度の判断は可能ですが、図面だけでは判断が難しい場合や、そもそも現況と図面が異なるケースもあります。
最も確実な方法は、リノベーション会社などの専門家に建物の構造を診断してもらうことです。プロによる調査で、抜けない柱の位置や役割を正確に把握し、安全なリノベーション計画を立てることができます。特に中古物件の場合は、購入前にリノベーション会社に相談し、希望する間取り変更が可能かどうか、抜けない柱がどこにあるかなどを確認しておくことがおすすめです。
押さえたいポイント
抜けない柱を活かしたリノベーションを成功させるためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
まず、抜けない柱を隠すのではなく、デザインの一部として見せることを検討しましょう。柱にアクセントとなる素材や色を取り入れることで、空間の個性を引き出すことができます。次に、柱の周囲のスペースを有効活用する計画を立てましょう。造作家具や棚を設置することで、収納スペースを確保したり、飾り棚として楽しんだりできます。
また、柱の位置を活かして空間をゆるやかに間仕切るゾーニングのアイデアも有効です。さらに、ハンモックやキャットウォークなど、柱の強度を利用したユニークな活用方法も検討に値します。
リノベーション会社と密に連携し、プロの視点からのアイデアや技術的なアドバイスを取り入れながら、抜けない柱を最大限に活かせる計画を進めることが重要です。必要に応じて柱の補強も視野に入れ、安全性を確保しながら理想の空間を実現しましょう。
まとめ:抜けない柱はおしゃれに活用しよう
リノベーションにおいて、構造上撤去できない柱は確かに存在します。しかし、抜けない柱があるからといって、理想の空間づくりを諦める必要はありません。抜けない柱は、リノベーションの制約ではなく、むしろ空間に個性や魅力をもたらす要素となり得ます。
ご紹介したように、見せる柱としてデザインのアクセントにしたり、造作家具や棚を設置して機能的に活用したり、空間の間仕切りとして利用したりと、様々なアイデアがあります。特にリビングなど家族が集まる空間では、抜けない柱を中心にコミュニケーションが生まれるようなデザインを取り入れることも可能です。マンションの場合でも、管理規約の範囲内で抜けない柱を活かしたリノベーションは十分可能です。
抜けない柱の位置や種類を正確に把握し、リノベーション会社と協力しながら、抜けない柱をおしゃれに活用する計画を立てて、理想の住まいを実現させてください。