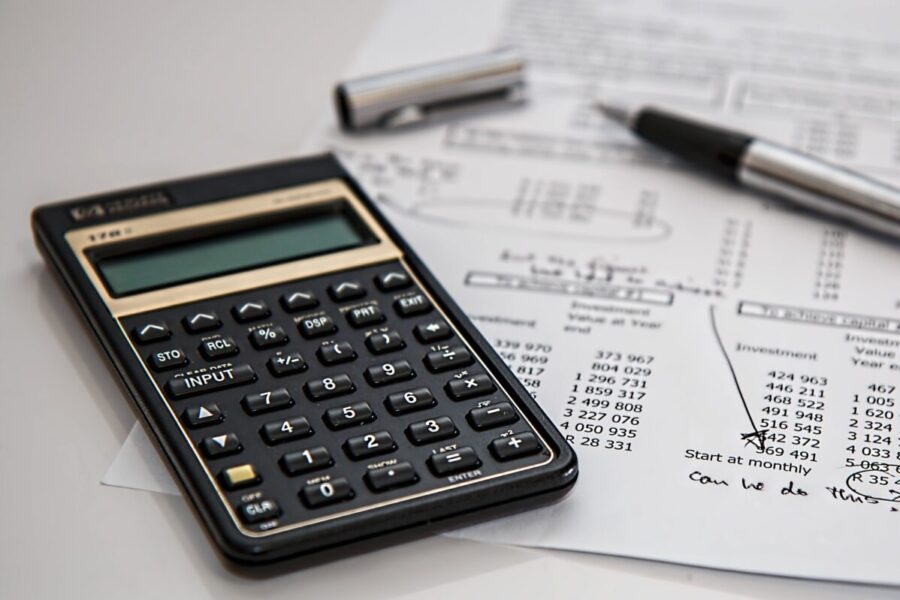【店舗・オフィス対象】建築基準法に基づき不燃材料を使用する内装制限について解説

 | Writer 柳川映子 デザイナーWORKS 大学院で建築を学び、二級建築士の有資格者でもあるので、ロジカルな設計を組み立てていくのが得意なデザイナー。 |
|---|
建築基準法に基づいた「内装制限」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。内装制限とは、万が一火災が起きてしまった際に建物内にいる人をスムーズに避難させ、火災発生時の被害を最小限におさえることを目的に、内装の際に不燃材料や準不燃材料の使用を義務付けているものです。内装制限は、用途に応じて異なる基準が設けられています。今回は、安全で快適な空間を構築するための「内装制限」について紹介します。
目次
内装制限とは?対象や基準を詳しく解説

内装制限とは、建築基準法に基づき建物の内部(壁や天井)に使用する仕上げ材や設備に対して、不燃材料を使用するという制約を設けているものです。不燃材料は火に強い性質を持つため、建物全体の防火性能を向上させます。これは、火災が起きてしまった際の延焼を防止し、安全な環境を確保することを目的としています。対象や基準について、下記に見ていきましょう。
建築基準法における内装制限の基本
内装制限の対象は、商業施設やオフィスビルなど不特定多数の人が集まる施設が主です。基準は用途や建物の規模によって異なり、それぞれの施設に応じた具体的な規定が存在します。内装制限の対象や基準を十分に理解することで、安全で快適な空間を構築します。
用途別に見る内装制限の対象範囲
内装制限では、建物の用途や床面積、耐火性能などによって対象範囲が設定されています。商業施設やオフィスビル、医療施設など、不特定多数の人が集まる場所では、より厳格な基準が設けられています。例えば、飲食店の場合は床面積200㎡以上だと内装制限がかかりますが、耐火建築物で2階以下なら不要になります。一方、工場や倉庫などの特殊な用途においては、内装制限の適用が異なります。
大規模建築物
大規模建築物においては、3段階に分かれています。
【A】3階建て以上で、延べ面積500㎡を越えるもの
【B】2階建てで、延べ面積1,000㎡を越えるもの
【C】1階建て(平家)で、延べ面積3,000㎡を越えるもの
上記に当てはまる場合は、戸建て住宅や事務所ビルなども内装制限の対象になります。例外もあり、「学校等」と呼ばれる学校・体育館・ボーリング場などは対象外となります。
無窓居室
窓が無い部屋も、内装制限の対象となります。50㎡以上の部屋において、煙を逃がすのに有効なサイズ(床面積の2%)以下、かつ、天井下80cm以内の高さに窓が無い場合です。居室だけでなく、その部屋から外部に出ることが出来る廊下や階段なども対象となります。
火気使用室
調理室などの火気使用室の場合は適応します。厳密にいうと、建築物が耐火構造かそうでないかで制限が変わります。耐火構造の建築物であれば制限を受けません。2階建て以上の場合は1階のみに適用となり、 平屋であれば対象外です。
壁や天井など内装仕上げ材の基準
壁や天井などの内装仕上げ材に関する基準は、建築基準法によって厳格に定められています。その基準は「床から1.2m以上の高さの壁~天井にかけて、燃えにくい資材の仕上げ剤を使用する」ことです。燃えにくい資材とは、燃えるのに時間がかかるもののことです。
特に火が広がるリスクが高い壁や天井は、これらの仕上げ材には不燃性が必要とされることが多いです。 不燃材の具体的な仕様や性能基準も、種類や用途によって異なるため、内装工事を行う際には明確な理解が求められます。
内装制限で求められる不燃材の種類と特徴
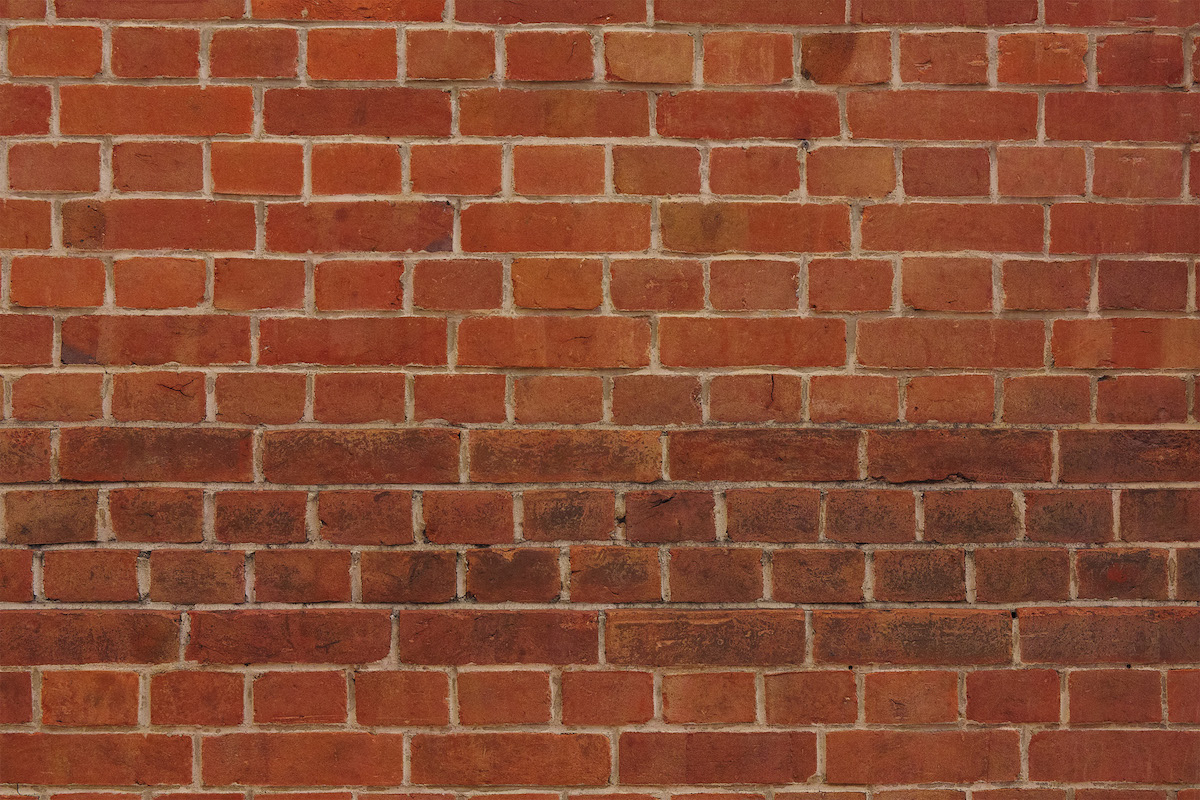
内装制限における不燃材の代表的な種類には、「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」があります。内装制限における不燃材の選定は、法律によって明確に定義されており、各メーカーはその基準を満たす製品を提供しています。内装制限で求められる不燃材の種類とその特徴を理解することは、安全で快適な空間を実現する上で重要な要素です。
不燃・準不燃・難燃材料の違い
「不燃材料」は、不燃材料は加熱開始後20分間防火材料の要件を満たすもの。
次のような種類があります。
●コンクリート
●れんが
●瓦
●陶磁器質タイル
●繊維強化セメント板
●厚さ3mm以上のガラス繊維混入セメント板
●厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
●鉄鋼
●アルミニウム
●金属板
●ガラス
●モルタル
●しっくい
●石
●厚さ12mm以上のせっこうボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6mm以下)
●ロックウール板
●グラスウール板
「準不燃材料」は、加熱開始から10分間要件を満たすもの。
次のような種類があります。
●厚さ9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さ0.6mm以下)
●厚さ15mm以上の木毛セメント板
●厚さ9mm以上の硬質木片セメント板
●厚さ30mm以上の木片セメント板
●厚さ6mm以上のパルプセメント板れんが
「難燃材料」は、加熱開始から5分間要件を満たすもの。
次のような種類があります。
●厚さ5.5mm以上の難燃合板
●厚さ7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下)
不燃木材とその特性について
不燃木材は、一般的に燃えやすいとされる木材に特殊な処理を施すことで木材が本来持つ可燃性をおさえ、不燃性を持たせたものです。見た目や質感を保ちながらも、内装制限に対応できることで注目されています。不燃木材は、環境への配慮からも重要視されており、デザイン性を兼ね備えながらも安全性を確保しています。
不燃パネルとその他の建材
不燃パネルは、不燃下地材に表面材を貼り合わせた化粧パネル材です。通常のビニールクロスやシートに比べ、より強い防火性能を持っています。特定の条件を満たしている不燃ボードは国土交通省認定品として明記されています。不燃パネルやその他の建材の特性を把握し、これを内装制限に活かすことで、より安全な空間を作り上げることができます。
内装制限の緩和条件と対象外のケース

内装制限における緩和条件は特定の要件を満たす場合に適用され、内装制限の対象外となるケースも存在します。この緩和を受けるためには、建築基準法に基づく厳密な基準を満たす必要があります。 一方、消防法との関連性も重要です。内装制限と消防法は異なる基準が設定されているため、両者を調整する必要があります。
具体的に緩和条件が適用されるには、一例として次のようなケースがあります。
●避難経路を含まない居室である
●11階建て以上でも、100㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く)が設けられている
●天井高さが3m以上である
●屋外へ直接避難できる出口がある
●スプリンクラーや水噴霧消火設備、泡消火設備などの自動式設備がある
実際は床面積や建物の構造なども関係してくるため、上記はあくまでも一例です。詳細は実際に検査を行う所轄消防署の判断によります。
木材に対する規制緩和の適用範囲と条件
「内装制限」の対象となる範囲に木材を用いる場合は、不燃・準不燃・難燃材料の認定を受けた建材を選ぶ必要があります。適用範囲や条件は、建物の用途や規模に、または地域によっても基準が異なります。木材の安全性を確保しつつ、デザイン性も担保でき、コスト面をおさえることも可能になります。
消防法との違いと調整のポイント
建築基準法に基づく「内装制限」と「消防法」は、いずれも防火対策に関連していますが、目的や対象が異なります。「内装制限」は建物全体の安全性を確保するための基準を定めており、主に内装材料の種類や仕上げに関する規制が中心です。一方、「消防法」は火災発生時の対応や避難を重視しており、特に避難経路や消火設備に関する規定が重要です。
内装制限は用途や規模によって異なるため、店舗やオフィスの設計段階で、消防法との整合性を考慮し、調整する必要があります。特に、不燃材料の選定や配置については、両者の要件が重複することが多くあります。調整をしないまま進めると、後に法的問題や安全リスクが生じる可能性もあるため注意が必要です。
例外的に対象外となる範囲や基準
内装制限には特定の範囲や基準が設けられていますが、例外的に対象外となるケースも存在します。例えば、施工面積が一定以下であったり、建物が特定の防火性能を有している場合においては、規制が緩和されることがあります。 また、特定の材料が使用されている場合においても、内装制限の対象外となるケースがあります。
店舗やオフィスで注意すべき内装制限

店舗やオフィスにおいて、内装制限は極めて重要です。計画段階で内装制限を考慮しないと、施工時にトラブルが生じ、改修工事が必要になるケースが多々あります。これにより、コストや工期が大幅に増加してしまいます。店舗やオフィスで注意すべき内装制限にはどんなものがあるか見ていきましょう。
計画段階で考慮するべき内装制限
特に、使用するサッシや塗装の選定も重要です。適切な材料を選ぶことで、内装制限に沿った安全な空間を創出できます。天井を6m以上まで高くすることが、オフィスに対する内装制限の緩和策として挙げられます。天井が高いと煙が充満する時間を遅らせて、火災初期の避難がしやすくなるからです。
事前確認で防ぐトラブル
内装制限を遵守しないことで発生するトラブルの事例は数多くあります。例えば、計画段階で不燃材料を選定しなかったために、消防の指導が入り工事が遅れたケースや、施工後に基準を満たしていないことが発覚し、修正工事が必要となった事態などが挙げられます。営業開始後であっても指摘を受けると、営業停止をせざるを得ないケースもあります。
サッシや塗装の選択時に知っておきたいこと
サッシや塗装の選択は、内装制限において重要なポイントです。まず、サッシは耐久性や断熱性が求められる一方で、内装基準に適合したものでなければなりません。特に不燃材料を使用する場合は、適切な製品を選択することが必要です。さらに、塗装の選択も重要です。塗装材には不燃性や難燃性のものがあり、これらを基準に選ぶことが内装制限を遵守する上で不可欠です。
内装制限に関わる建築基準法と法改正
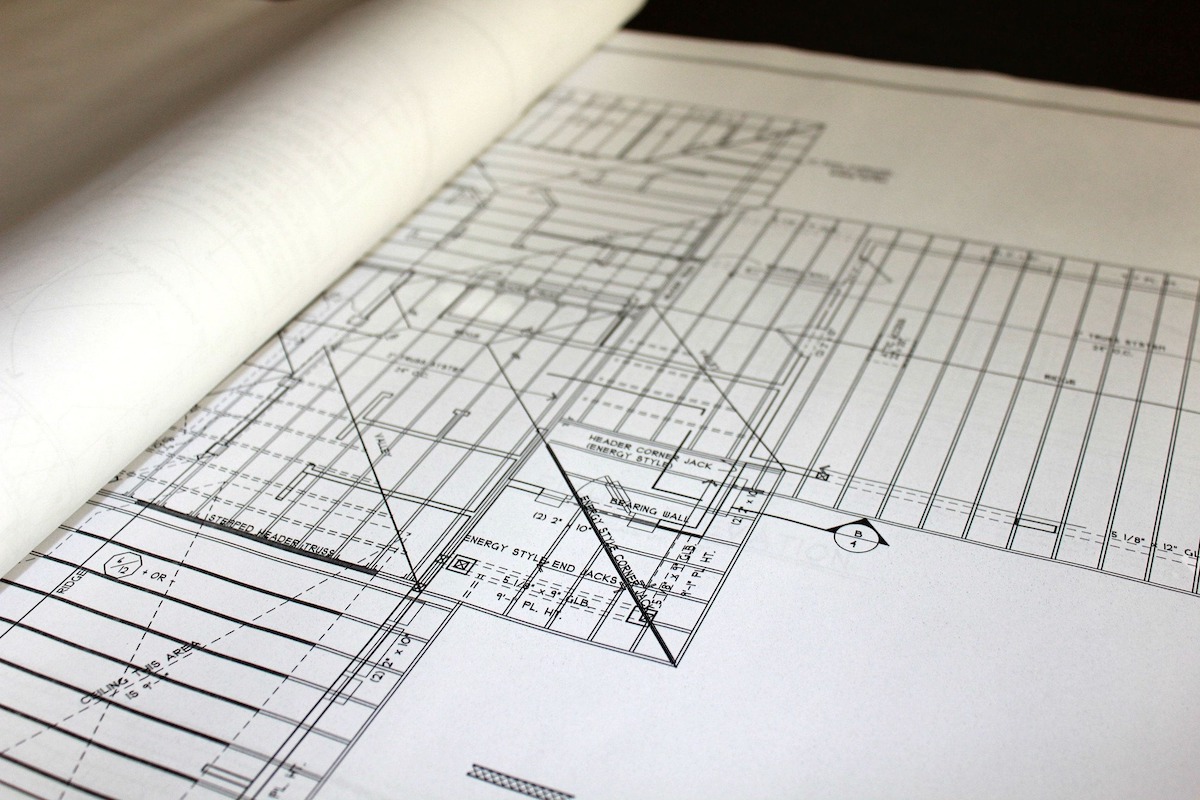
内装制限は建築基準法に基づく重要な規定です。内装制限の対象は用途によって異なり、基準も細分化されています。例えば、住宅と商業施設では求められる基準が異なるため、正確に把握することが重要です。また、内装制限は定期的に見直されているため、建築の際はアップデートされた内容を確認しましょう。内装制限を遵守しないと建築基準法違反となり、個人は懲役3年以下または罰金300万円以下、法人は一億円以下の罰金が課せられる可能性があります。
2025年の法改正で変わる基準と範囲
2025年の法改正では、内装制限の基準や対象範囲が見直され、特に倉庫や店舗に対する新たな規定が追加される予定です。不燃材料の使用が義務付けられるエリアや、特定の用途に応じた柔軟な適用が検討されています。また、地域や建物の用途に基づいて内装制限が異なるため、特定の条件下で緩和措置が適用される可能性もあります。
これにより、過去の基準では使用不可能だった材料にも、新たな選択肢が生まれることになります。この法改正は、内装材選びや施工においても大きな影響を及ぼします。法改正を踏まえた建築計画を立てましょう。
倉庫や店舗における最新の内装制限
倉庫や店舗における内装制限は、建築基準法に基づく安全基準の一環です。これにより、可燃物の使用が制限され、火災時の被害拡大を防ぎます。特に倉庫や店舗では、広い空間を有効に活用するために、壁や天井の仕上げ材に関する制約が重要です。
内装制限は、その用途に応じて異なる基準が設定されており、各施設の特性に応じて安全性を確保します。例えば、倉庫においては高い天井や広い空間に適した不燃材の使用が求められ、店舗では顧客の目に触れる場所においても安全が重視されます。これらの制限を遵守することで、必要な防火対策が施され、安全で安心な環境を提供できます。
内装制限対象の一覧と材料選び

内装制限に対応するために、要となる材料選び。建築基準法を遵守しつつも、店舗やオフィスの機能性やデザインを保持することができる重要なポイントです。ここでいま一度、内装制限対象の一覧と不燃・準不燃材料の特徴比較について一覧にまとめました。
内装制限対象の一覧
| 用途 | 対象となる条件 | 内装制限の内容 |
| 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | (耐火建築物)客席400㎡以上 | 居室:難燃材料 |
| (準耐火建築物)客席100㎡以上 | 通路など:準不燃材料 | |
| (その他の建築物)客席200㎡以上 | 病院、診療所(患者の収容施設のあるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 | (耐火建築物)3階以上の部分300㎡以上 | 居室:難燃材料 |
| (準耐火建築物)2階部分300㎡以上 | 通路など:準不燃材料 | |
| (その他の建築物)2階部分200㎡以上 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業 | (耐火建築物)3階以上の部分1,000㎡以上 | 居室:難燃材料 |
| (準耐火建築物)2階部分500㎡以上 | 通路など:準不燃材料 | |
| (その他の建築物)2階部分200㎡以上 | ||
| 地階の居室等で上記用途のもの | すべて対象 | 居室:準不燃材料 |
| 通路など:準不燃材料 | 自動車車庫、自動車修理工場 | すべて対象 | 居室:準不燃材料 |
| 通路など:準不燃材料 | 無窓の居室 | すべて対象(天井高6m超えるものを除く) | 居室:準不燃材料 |
| 通路など:準不燃材料 | 火気使用室 | (住宅)二階以上で最上階以外が対象 | 火気使用室:準不燃材料 |
| (住宅以外)すべて対象 | 大規模建築物 | (3階建て以上)500㎡を超える | 居室:難燃材料 |
| (2階建て)1,000㎡を超える | 通路など:準不燃材料 | |
| (1階建て)3,000㎡を超える | 地下街 | 100㎡以内に防火区画された部分 | 居室:準不燃材料 |
| 200㎡以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 | 通路など:不燃材料 | |
| 500㎡以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 |
不燃・準不燃材料の特徴比較
| 比較項目 | 不燃木材 | 天然木突板貼り不燃パネル |
| 質感 | ・無垢材と同様の柔らかい質感 | ・無垢材よりも硬く冷たい質感 |
| ・分厚い塗膜の塗装も可能(重厚感や高級感) | ・薄い塗膜の塗装が基本(軽やかでカジュアルな印象) | |
| 価格帯 | ・かなり高価 | ・樹種によって価格は変動するが比較的安価 |
| (10,000円/㎡〜) | (6,000円/㎡〜) | |
| 形状 | ・面取り加工、殴り加工、目透かし加工など様々な形状に対応可 | ・面取り加工、殴り加工、目透かし加工など表面に凹凸の出る加工は対応不可 | →自由度が高い | →表面材(突板)が薄いため、平面的な形状以外には不向きで自由度は低い |
| ・不燃パネルよりも分厚くなるため、重量があり細かい納まりに対応しづらい | ・厚さ6mmのラインナップがあるため、材料の軽量化がはかれて細かい納まりにも対応できる | |
| 耐用年数 | ・施工環境によっては薬剤が溶け出すことでの白華リスクあり | ・屋内施工が原則 |
| ・使用環境が整っていれば不燃パネルよりも耐用年数は長い | ・使用環境による耐用年数の変動リスクは不燃木材ほどない | |
| ・突板と基材の接着面が経年劣化するため、不燃木材よりも耐用年数は短い | 樹種 | ・杉と桧が大半で樹種のレパートリーは少ない | ・国内外の様々な樹種に対応できるため、レパートリーは多い |
まとめ:内装制限に正しく対応するために
建物の火災のリスクを低減できる内装制限。店舗・オフィスの建築を検討している場合は、建築段階で必ず視野に入れておく必要があります。正しく対応するためには、建築基準法に基づく基準を遵守することが不可欠です。建築の計画段階から内装材料や仕上げに関する基準を確認し、適切な不燃材や準不燃材を選定する必要があります。 また、消防法との調整や、緩和条件についても把握しておく必要があります。また、内装制限の規定は定期的に見直されているため、建築の際はアップデートされた内容を確認しましょう。