リフォーム・リノベーションの経費計上で節税!不動産・マンション経営の費用処理
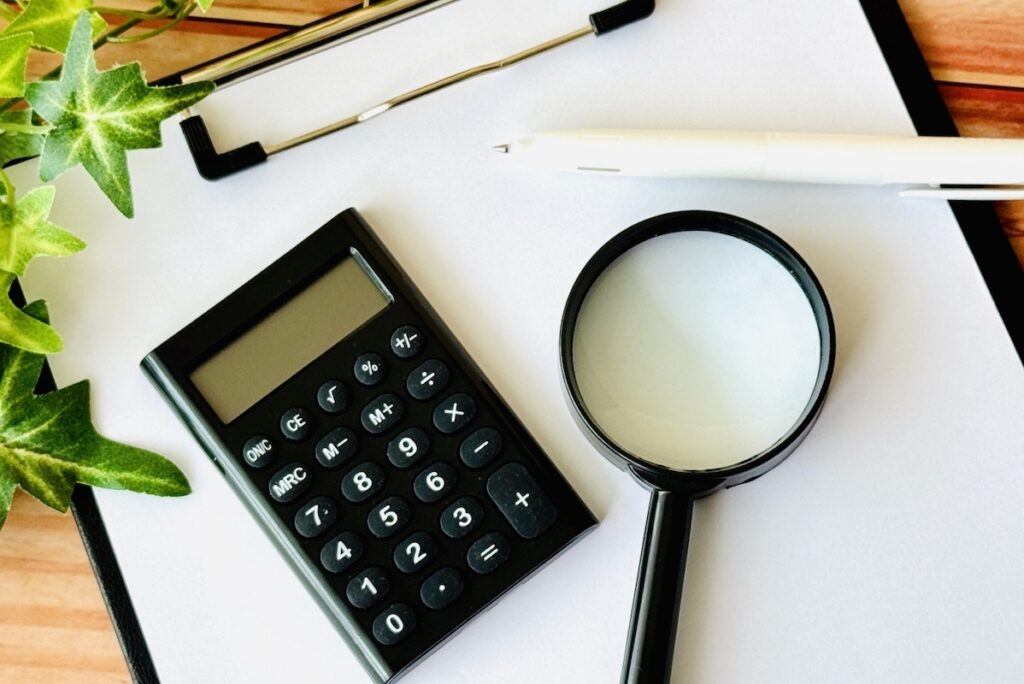
こんにちは!クジラ株式会社の山根です!
 | Writer 山根広大 ディレクターWORKS 宅地建物取引士。大学で建築を学び、人の暮らしにより幅広く関わりたいと思い不動産業界を志望。2019年にクジラ株式会社に入社。不動産・建築の両面からワンストップでリノベーションをサポートするのが得意。 |
|---|
賃貸物件のリフォームやリノベーションにかかる費用は、経費計上の方法によって節税効果が大きく変わります。不動産経営において、この費用を正しく会計処理することは、キャッシュフローを安定させる上で極めて重要です。
支出の内容に応じて「修繕費」として一括で経費にするか、「資本的支出」として資産計上し減価償却するかを適切に判断しなければなりません。この選択が、その年の納税額だけでなく、長期的な経営計画にも影響を及ぼします。
目次
リノベーション費用は経費になる?知っておきたい2つの勘定科目

リノベーションにかかった費用を経理処理する際、使われる勘定科目は主に「修繕費」と「資本的支出」の2種類に大別されます。どちらの科目で処理するかによって、経費として計上できるタイミングと金額が異なり、納税額に直接影響します。
支出の実態に合わせて、どちらに該当するかを正しく見極めることが、適切な会計処理と節税の第一歩。この2つの違いを正確に理解し、適切に分類する知識が求められます。
原状回復が目的の「修繕費」
修繕費とは、賃貸物件を維持管理したり、故障した箇所を元の状態に戻したりするための原状回復にかかる費用を指します。
具体的には、退去者が出た後の壁紙の張り替え、壊れた給湯器の修理、外壁塗装の塗り直しなどが該当します。これらは資産の価値を新たに付け加えるものではなく、あくまでも通常のコンディションを保つための支出と見なされるのが特徴。
会計処理上、修繕費は支出したその年の経費として一括で計上することが認められており、資産計上は必要ありません。これにより、その年の課税所得を直接的に圧縮できます。
資産価値を高める「資本的支出」
資本的支出は、リフォームやリノベーションによって物件の価値を向上させたり、使用可能な期間(耐用年数)を延長させたりするための支出を意味します。
例えば、間取りを変更して現代的なデザインにする、最新のシステムキッチンを導入する、建物の耐震補強工事を行うといったケースがこれにあたります。500万円を投じるような大規模な機能向上リノベーションも、通常は資本的支出と判断されます。
この支出は資産の取得と見なされるため、一度資産計上した上で、減価償却という手続きを経て法定耐用年数にわたって分割して経費化していきます。
修繕費か資本的支出かを見分ける4つの判断基準

リノベーション費用が修繕費と資本的支出のどちらに分類されるかは、税務上の判断が非常に重要になります。
明確な線引きが難しいケースも少なくありませんが、国税庁はいくつかの形式的な基準や実質的な判断基準を示しています。
実務上は、工事にかかった金額、修繕の周期、そして工事の内容が資産価値を向上させるものか否かといった点を総合的に勘案して判断します。ここでは、その判断に役立つ代表的な4つの基準を解説します。
基準1:工事費用が20万円未満か
一つの工事にかかった費用が20万円未満の場合、その支出は原則として修繕費として処理することが認められています。
この基準は、工事の内容が資産の価値を高めるようなものであったとしても適用される、形式的な判断基準の一つです。
例えば、18万円かけて旧式の設備を最新のものに交換した場合でも、金額が20万円未満であるため修繕費として一括計上が可能です。ただし、本来一つの工事であるものを意図的に分割して20万円未満に見せかけるような処理は、税務調査で否認されるリスクがあるため注意を要します。
基準2:修繕の周期が概ね3年以内か
概ね3年以内の周期で行われることが明らかな修繕や改良は、金額の多寡にかかわらず修繕費として扱われます。
これは、その支出が資産の維持管理や機能の維持を目的とした定期的なメンテナンスの一環であると解釈されるためです。例えば、2年ごとに行う外壁の塗装や、定期的な共用部のメンテナンスなどがこれに該当します。
この基準は、計画的な維持管理費用の経費処理を円滑にするためのものです。しかし、明らかに資産価値を向上させる大規模な工事を意図的に短い周期で行う場合、実態に応じて資本的支出と判断されることもあります。
基準3:資産の価値や耐久性を高める工事か
支出の内容が、物件を元の状態に戻す「原状回復」のレベルを超えて、資産の価値を明らかに増加させたり、耐久性を向上させたりするものである場合、その支出は資本的支出に該当します。
これが最も本質的な判断基準です。例えば、単なる壁紙の交換ではなく断熱材を追加する、和室をフローリングの洋室へ変更するといった工事は、資産価値の向上と見なされます。
また、建物の耐震補強工事や非常階段の設置なども、耐久性や安全性を高めるため資本的支出に分類されます。税務調査においても、この実質的な価値向上の有無が重視されます。
基準4:判断に迷う場合は割合で按分する方法も
一つの工事に修繕費と資本的支出の両方の性質が含まれており、明確な区分が困難なケースも存在します。
その場合、支出額の30%相当額とその資産の前年末における取得価額の10%相当額の、いずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出として按分する経理処理が認められています。
また、支出額が60万円未満であれば修繕費として処理できる基準も存在します。これらのルールは判断に迷った際の指針となりますが、税務上の解釈は複雑なため、税理士などの専門家への相談が確実でしょう。
経費計上の方法で節税効果が変わる!2つの会計処理

修繕費と資本的支出では、経費を計上する会計処理の方法とタイミングが根本的に異なります。この違いが、各事業年度の利益額、ひいては納税額に直接的な影響を及ぼすことになります。
修繕費は単年度の利益を圧縮する効果がある一方、資本的支出は複数年にわたり費用を平準化します。
どちらの処理を選択すべきかは、その年の収益状況や今後の事業展開の見通しによって変わるため、それぞれの会計処理がもたらす効果を正確に理解しておくことが不可欠です。
修繕費は一括で経費にしてその年の税金を抑える
修繕費として認められた支出は、その費用が発生した事業年度において全額を経費として計上できます。
これにより、その年の課税対象となる所得を直接的に圧縮することが可能となり、結果として所得税や法人税の負担を軽減する即時的な効果が期待できます。
特に、賃貸収入が多く大きな利益が見込まれる年に計画的な修繕を行うと、節税効果はより高まります。例えば、400万円の利益に対して200万円の修繕費を計上すれば、課税所得は200万円に減少します。短期的なキャッシュフローを改善したい場合や、特定の年に利益が偏った際に有効な方法です。
資本的支出は減価償却で複数年にわたり経費計上する
資本的支出と判断された費用は、支出した年に一括で経費にはできません。まず、その金額を建物の取得価額に加算して資産として計上します。
その後、「減価償却」という会計手続きを通じて、法律で定められた耐用年数にわたって毎年分割して経費化していきます。この方法では、単年度の利益を大きく変動させることなく、長期にわたって安定的に経費を計上し続けることが可能です。
これにより、毎年の所得を平準化し、安定した経営基盤を外部に示す効果もあります。将来にわたり継続的な収益が見込める不動産経営に適した処理方法と言えます。
資本的支出と判断された場合の減価償却の仕組み

資本的支出と判断されたリノベーション費用は、減価償却を通じて経費化されます。
このプロセスを理解するためには、「減価償却」という会計上の考え方と、資産の構造によって定められる「法定耐用年数」についての知識が不可欠です。
資産価値の減少分を、法律で決められた年数にわたって費用として配分するこの仕組みは、不動産経営における損益計算の根幹をなす重要なルールです。ここでは、減価償却の基本的な概念から、実際の計算方法までを具体的に説明します。
減価償却とは?費用を数年に分けて計上する考え方
減価償却とは、建物や設備といった高額な固定資産の取得費用を、その資産が使用できる期間(法定耐用年数)に応じて分割し、毎年少しずつ経費として計上していく会計上の手続きです。
特に、マンションなどの不動産経営において、この減価償却の考え方は非常に重要です。資産は時間の経過や使用によってその価値が徐々に減少していくという考え方に基づいています。例えば、マンションの購入費用や大規模なリノベーション費用は、購入した年に全額を経費にするのではなく、資産が生み出す収益に対応させて費用を配分することで、各事業年度の損益をより正確に把握することが目的です。
実際にお金の支出がない年にも経費を計上できるため、帳簿上の利益を抑える効果があり、マンションの確定申告をする際には重要な節税対策の一つとなります。
建物の構造によって決まる法定耐用年数
減価償却費を計算する上で基礎となる期間が法定耐用年数であり、これは資産の種類や構造、用途によって税法で詳細に定められています。
事業用の建物の場合、例えば木造であれば22年、軽量鉄骨造(骨格材の厚さが3mm超4mm以下)は27年、鉄筋コンクリート造(RC)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)は47年と規定されています。
リノベーション費用(資本的支出)は、既存の建物本体の価値を高めるものとして扱われるため、原則としてその建物の法定耐用年数を適用して減価償却を行います。所有物件の構造と耐用年数を正確に把握することが計算の前提となります。
リノベーション費用の減価償却費の計算方法
個人事業主が行う不動産賃貸業における建物の減価償却は、原則として定額法という方法で計算します。
定額法では、毎年均等な額の減価償却費を計上します。計算式は取得価額×定額法の償却率です。リノベーション費用(資本的支出)は、この取得価額に加算されます。
償却率は法定耐用年数に応じて決まっており、例えば耐用年数22年(木造)の場合は0.046、耐用年数47年(RC造)の場合は0.022です。
仮にRC造の物件に300万円の資本的支出を行った場合、年間の減価償却費は300万円×0.022=6万6,000円となります。
節税だけじゃない!経費計上する前に知っておきたい注意点

リノベーション費用の経費計上を検討する際、節税効果だけに注目するのは視野が狭いかもしれません。選択した会計処理の方法は、金融機関からの融資審査における評価や、中長期的な事業計画にも少なからず影響を及ぼすからです。
短期的な税負担の軽減を優先する判断が、必ずしも経営全体にとって最良の選択とは限りません。経費計上を実行する前に、節税以外の側面にも目を向け、多角的にその影響を考慮することが重要です。ここでは、そうした注意点を解説します。
資産計上は金融機関からの評価を高める可能性がある
リノベーション費用を資本的支出として資産計上すると、貸借対照表における総資産額が増加します。金融機関が融資審査を行う際、この総資産額や自己資本比率は企業の財務体質を判断する重要な指標の一つです。資産が増加することで財務内容が充実していると評価され、信用力が高まる可能性があります。
また、利益が単年度で急激に減少することがないため、収益の安定性を示すことにもつながります。将来的に事業拡大のための追加融資を検討している場合、修繕費として一括経費計上するよりも有利に働く場面が考えられます。
一括での経費計上が必ずしも有利とは限らない理由
修繕費として一括で経費計上する手法は、その年の課税所得を大きく圧縮しますが、一方で利益が大幅に減少、あるいは赤字決算となる可能性があります。単年度の節税効果は高いものの、金融機関からは収益性の低い事業と見なされたり、経営が不安定であると判断されたりするリスクを伴います。特に赤字決算は、新規の融資や借換えの審査において不利な材料となることが少なくありません。
また、もともと課税所得が少ない年に多額の修繕費を計上しても、その節税効果は限定的です。目先の税金だけでなく、財務諸表全体への影響を考慮した判断が求められます。
リフォーム・リノベーションの経費計上は将来を見据えて!
リノベーション費用は「修繕費」または「資本的支出」として経理処理され、どちらを選択するかで節税効果や財務状況への影響が大きく異なります。
修繕費は一括経費計上により短期的な節税効果が高い一方、資本的支出は減価償却を通じて資産計上するため、長期的な経営の安定化や金融機関からの評価向上に寄与する場合があります。20万円未満の工事か、資産価値を高める内容かといった基準で判断しますが、実務上は区分が難しいケースも少なくありません。
自身の経営戦略や将来の事業計画を考慮し、最適な経費計上の方法を選択することが重要です。




