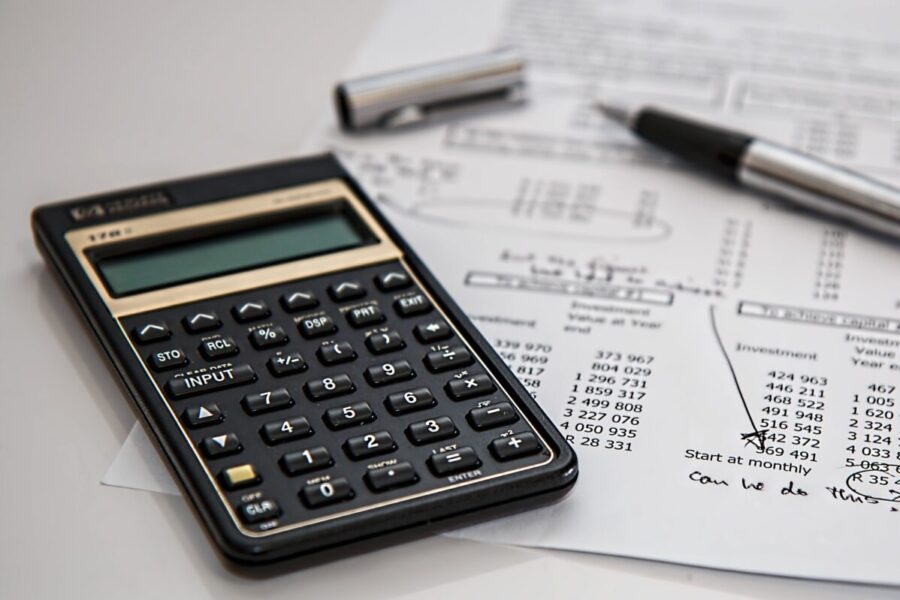リフォーム・リノベーションが相続税対策に!計算方法や注意点とは

こんにちは!クジラ株式会社の髙谷です!
 | Writer 髙谷 佑樹 ディレクター リノベーションは日々の暮らしに明かりを灯してくれる魔法だと思っています。お客様の心と暮らしに寄り添うリノベーションを精一杯お手伝いさせていただきます! |
|---|
相続税対策として、所有する不動産、特に自宅のあり方に関心を持つ方は多いです。その中でも、リフォームやリノベーションが相続税対策になり得ることも。リフォーム・リノベーションが相続税対策になるのはなぜか、具体的な計算方法や贈与税の注意点について解説します。
目次
リフォーム・リノベーションが相続税対策になる理由

相続税対策としてリフォームやリノベーションが有効とされるのは、主に「基礎控除が縮小されたため」「リフォーム・リノベーションをしても相続税評価額が上がらないため」という2つの理由が挙げられます。
基礎控除が縮小されたため
平成27年1月1日以降の相続から、相続税の基礎控除額が縮小されました。これにより、相続税の課税対象となるケースが増加しています。改正前の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は改正前が8,000万円であったのに対し、改正後は4,800万円となり、3,200万円も縮小されています。この基礎控除の縮小により、以前は相続税の申告が不要だった場合でも、申告が必要になるケースが増えています。相続税の負担が増える可能性が高まったことから、相続税対策への関心が高まっており、リフォーム・リノベーションもその選択肢の一つとして注目されています。
リフォーム・リノベーションをしても相続税評価額は上がらないため
建物にかかる相続税は、固定資産税評価額を基に計算されます。一般的に、建物の固定資産税評価額は築年数の経過とともに減少していくもの。通常の維持管理や原状回復を目的としたリフォームやリノベーションでは、建物の固定資産税評価額が大きく上昇することは少ない傾向があります。これは、あくまで建物を元の状態に戻したり、現状の機能を維持したりするための費用とみなされるためです。
そのため、手元にある現金を使ってリフォームやリノベーションを行うことで、相続財産である現預金を減らすことができますが、建物の評価額はそれに比例して大きく増えないことが多く、結果的に相続財産全体の評価額を抑えることにつながり、相続税対策として有効な場合があります。
ただし、増築など建物の構造や規模を大きく変えるリフォームの場合は、評価額が上昇する可能性があるので注意が必要です。
相続税評価額の計算方法

建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額を使用します。しかし、リフォームやリノベーションを行った場合には、その内容によって評価方法が異なることも。特に相続発生の直前にリフォームを行った場合など、固定資産税評価額にリフォームによる価値の変動が反映されていないケースでは、別途評価額を計算する必要があります。
固定資産税評価額が改定される場合
建物の固定資産税評価額は通常3年に一度評価替えが行われますが、増築や、建物の種類を変えるような大規模な改築を行った場合には、その都度固定資産税評価額が改定されることがあります。相続が発生した際に、既にリフォームによる影響が固定資産税評価額に反映されている場合は、その改定後の固定資産税評価額を基に相続税評価額を計算します。
この場合、新たにリフォーム費用を加算して評価額を計算する必要はありません。評価替えの有無は、固定資産税の課税明細書で確認することができます。もし相続税の申告期限までに固定資産税評価額の改定が行われていれば、その新しい評価額で申告することが可能です。
固定資産税評価額が改定されない場合
リフォームやリノベーションを行った場合でも、増築を伴わない内装の改修など、固定資産税評価額がすぐに改定されないことがあります。特に相続発生の直前にリフォームを行った場合、固定資産税評価額にリフォーム費用による価値の上昇が反映されていない可能性が高いです。このようなケースでは、リフォーム前の固定資産税評価額に、リフォーム費用を加算して相続税評価額を計算する必要があります。
国税庁の指針では、リフォームした建物全体の相続税評価額は、リフォーム前の建物の固定資産税評価額にリフォーム費用の価額を加算して求めることとされています。リフォーム費用の価額は、原則として個別に評価することになりますが、実務では、リフォームに要した費用の額から償却費相当額を控除した金額に70%を乗じて計算することが一般的です。償却費相当額は、リフォームからの経過年数と建物の耐用年数に基づいて計算されます。
リフォーム・リノベーションの内容による評価の違い
リフォームやリノベーションが建物の相続税評価額に与える影響は、その工事の内容によって異なります。建物の価値を維持するための原状回復やメンテナンスを目的とした修繕費用は、原則として相続税評価額に加算する必要はありません。これには、例えば壁紙の張り替え、水漏れの修理、老朽化した設備の交換などが該当します。これらの費用は、建物の機能や性能を向上させるものではなく、現状を維持するための支出とみなされるためです。
一方、建物の価値を向上させたり、耐久年数を延ばしたりするようなリフォーム・リノベーションは「資本的支出」とみなされ、相続税評価額に加算する必要があります。具体的には、増築による床面積の増加、建物の用途変更を伴う改修、設備のグレードアップなどがこれに該当します。相続税対策としてリフォーム・リノベーションを検討する際には、どのような工事が評価額に影響を与えるのかを理解し、工事内容を選択することが重要になります。
相続税対策としてのリフォーム・リノベーションの種類

相続税対策として有効なリフォーム・リノベーションにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴と税務上のメリット・デメリットが存在します。対策を検討する際には、ご自身の資産状況やご家族構成、将来のライフプランに合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。ここでは、相続税の負担軽減につながる可能性のある代表的なリフォームについて解説します。
二世帯住宅へのリフォーム
自宅を二世帯住宅にリフォームすることは、相続税対策として有効な手段の一つです。二世帯住宅にすることで、敷地面積が広くても「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があり、土地の評価額を最大80%減額できる場合があります。この特例の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、特に親と同居している子などが家を相続する場合に大きな節税効果が期待できます。
また、二世帯住宅にすることで、親世帯と子世帯が同居することになり、将来的な介護の負担軽減や、孫との同居による賑やかな生活など、税金面以外のメリットも得られます。ただし、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、建物の構造や登記方法に注意が必要となるため、事前に専門家へ相談することが大切です。
賃貸併用住宅へのリフォーム
自宅の一部を賃貸スペースとする賃貸併用住宅へのリフォームも、相続税対策として検討される方法の一つ。賃貸に出している部分は「貸家建付地」として土地の評価額が下がり、建物も貸家として評価されるため、相続税評価額を抑えることができます。
また、家賃収入を得られるため、相続発生後の収益源を確保できるというメリットもあります。賃貸併用住宅の場合も、二世帯住宅と同様に小規模宅地等の特例の適用を受けられる可能性がありますが、賃貸部分には特例が適用されず、居住部分のみが対象となるため、評価額の計算には注意が必要。
リフォームにかかる費用と将来得られる家賃収入、そして相続税の軽減効果を総合的に判断し、計画を進めることが重要です。
価値を上げないリフォーム
相続税対策としてリフォームを行う場合、建物の価値を不必要に上げないリフォームを選択することも有効です。建物の相続税評価額は固定資産税評価額に基づいているため、固定資産税評価額が上昇するような大規模な改修や増築は、相続税評価額を上げてしまう可能性があります。そのため、あくまで建物の維持管理や老朽化した設備の交換といった、原状回復を目的としたリフォームに留めることで、手元にある現預金を減らしつつ、建物の評価額を大きく変えないという方法が考えられます。
例えば、外壁の塗り替え、水回りの設備の交換、内装の一般的な修繕などがこれに該当します。これらのリフォームは、建物の快適性や機能性を維持・向上させる一方で、資産価値を大きく引き上げるものではないため、相続税対策として有効な場合があります。ただし、リフォームの内容が修繕費と資本的支出のどちらに該当するかによって税務上の扱いが異なるため、事前に専門家に確認することをお勧めします。
リフォーム資金と贈与税

リフォームやリノベーションを行う際の資金を親や祖父母から援助してもらう場合、贈与税がかかる可能性があります。しかし、住宅取得等資金の贈与に関しては非課税となる特例があり、これを活用することで税負担を軽減できます。ここでは、リフォーム資金に関する贈与税について詳しく見ていきます。
住宅取得等資金の贈与税非課税
直系尊属(父母や祖父母など)から、自己が居住する家屋の新築、取得または増改築等のための資金の贈与を受けた場合、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」という特例が適用されることがあります。この特例を利用すると、一定の要件を満たせば、最大1,000万円(省エネ等住宅以外の場合は500万円)までの贈与が非課税となります。
この制度は、令和4年度の税制改正により適用期限が延長され、令和8年12月31日までとなっています。非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の1月1日時点で贈与を受けた人が18歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)、リフォームの工事費用が100万円以上であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
また、贈与を受けた翌年の3月15日までにリフォームを完成させ、居住を開始する見込みであることも条件となります。
生前贈与の注意点
リフォーム資金を目的とした生前贈与を検討する際には、いくつか注意すべき点があります。まず、年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されるため、非課税枠を超える金額を贈与する場合には贈与税の申告が必要となります。贈与税の申告を怠ると、延滞税や加算税が課される可能性があるので注意が必要です。
また、親から子へのリフォーム資金の贈与には住宅取得等資金の非課税特例が適用される可能性がありますが、子から親へのリフォーム費用の援助は原則として贈与税の対象となり、非課税特例は適用されません。
さらに、相続開始前一定期間内の贈与は、相続税の計算において相続財産に加算される「生前贈与加算」の対象となる場合があります。令和6年1月1日以降の贈与に関しては、加算期間が相続開始前7年間に延長されました。相続税対策として生前贈与を行う場合は、長期的な視点で計画を立てることが重要です。
費用負担と贈与税
リフォーム費用の負担割合と贈与税の関係にも注意が必要です。
例えば、親名義の家のリフォーム費用を子が全額負担した場合、子が親にリフォーム費用を贈与したとみなされ、贈与税が課税される可能性があります。特に親子共有名義の建物をリフォームする際には、費用負担の割合と持ち分の割合が一致していないと、贈与とみなされることがあります。
このような場合は、事前に費用負担割合に合わせて名義変更を行うことで、贈与税の負担を抑えられる可能性があります。リフォーム費用を誰がどのくらい負担するのか、そしてそれによって贈与税が発生するのかどうかを事前に確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することが重要です。
リフォームと相続税の注意点

リフォームやリノベーションを相続税対策として検討する際には、いくつかの重要な注意点があります。かえって税負担が増えたり、予期せぬ問題が発生することを防ぐため、注意点を確認しておきましょう。
リフォーム費用の申告
相続発生前にリフォームを行った場合、リフォーム費用を適切に申告する必要があります。特に、リフォームによって建物の価値が向上したとみなされる「資本的支出」に該当する費用は、相続税評価額に加算して申告しなければなりません。
相続税の申告時には、リフォームにかかった費用の明細や領収書などが必要となります。税務署は、相続財産の中に預貯金の大きな減少がある場合や、相続直前に多額の現金の動きがあった場合に、その資金の使途について確認することがあります。リフォーム費用として正しく申告しない場合、相続税の申告漏れを指摘され、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があるので注意が必要です。
リフォーム費用の申告方法や、どの費用が相続税評価額に加算されるのかについて不明な点がある場合は、税理士に相談することをお勧めします。
共有名義の建物のリフォーム
共有名義となっている建物をリフォームする場合、リフォーム費用を誰がどのくらいの割合で負担したかによって、贈与税が発生する可能性があります。
例えば、子と親で共有している建物をリフォームする際に、親がリフォーム費用を全額負担した場合、子が負担すべき部分の費用を親が代わりに支払ったことになり、親から子への贈与とみなされることがあります。
共有名義の建物におけるリフォーム費用の負担は、共有持分の割合に応じて行うのが原則です。もし持分割合と異なる割合で費用を負担する場合には、その差額に対して贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。
相続発生直前のリフォーム
相続発生の直前に大規模なリフォームを行った場合、そのリフォーム費用が相続財産に加算される可能性が高くなります。これは、相続税評価額にリフォームによる価値の向上が反映されていない場合に、リフォームにかかった費用を基に評価額を計算するためです。
税務署は、相続開始前に行われた大きな現金の支出に注目することがあります。相続発生直前のリフォームは、相続税を減らすための意図的な行為とみなされる可能性もゼロではありません。そのため、相続直前のリフォームを検討する際は、なぜその時期にリフォームを行うのか、その目的や必要性を明確にし、リフォーム内容や費用について記録を整理しておくことが重要です。
リフォーム中の相続
リフォーム工事の途中で相続が発生した場合、工事の進捗状況や費用の支払い状況によって、相続財産の評価や債務控除の対象となる金額が変わるため注意が必要です。工事が完了しておらず、まだ支払いが済んでいない工事費用がある場合は、未払金として相続財産から差し引くことができる可能性があります。
一方、既に工事が完了している部分については、その分のリフォーム費用を建物の相続税評価額に加算して評価する必要があります。リフォーム工事中に相続が発生するというケースは稀ですが、その場合の財産評価は複雑になることがあります。
工事請負契約の内容や、工事の進捗状況、支払い状況などを正確に把握し、適切な相続税の申告を行うためには、速やかに税理士に相談し、専門的なアドバイスを受けることが重要です。
二世帯住宅の登記方法
二世帯住宅にリフォームした場合、相続税対策として小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、建物の登記方法が重要な要素となります。二世帯住宅の登記方法には、「区分登記」と「一体登記」の2つの方法があります。
区分登記は、親世帯部分と子世帯部分をそれぞれ独立した建物として登記する方法です。この場合、各世帯がそれぞれ所有権を持つことになります。
一体登記は、建物全体を一つの建物として登記する方法です。この場合、親子で共有名義とするケースが多く見られます。小規模宅地等の特例の適用要件は、登記方法によって判断が異なる場合があります。特に一体登記で共有名義とする場合、特例の適用を受けるためにはいくつかの細かい要件を満たす必要があるため注意が必要と言えるでしょう。
相続税対策のリフォーム・リノベーションは施工内容に注意!
現預金を建物へ変えることで相続財産の圧縮が期待できますが、内容によっては相続税評価額を逆に引き上げてしまう場合もあります。また、リフォーム・リノベーション費用が贈与と見なされると贈与税が課される可能性も。
さらに、相続直前のリフォーム・リノベーションや工事中の相続発生など複雑なケースも想定されます。相続税対策としてリフォーム・リノベーションを行う際は、税務リスクや効果を事前に確認し、税理士など専門家に相談しながら進めることが重要です。
▼こちらの記事もご参考ください!
葬儀後の相続は何から始める?「遺産相続」手続きの流れ|公益社