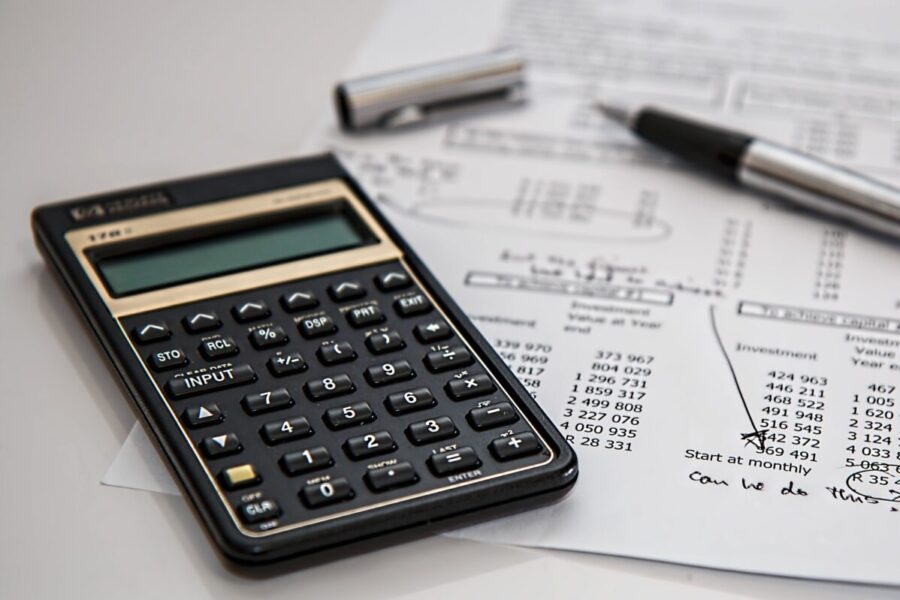コンクリート打ちっぱなしの施工事例多数!メリット・デメリットと対策、費用ついて

こんにちは!クジラ株式会社の片山です!
 | Writer 片山飛翔 デザイナーWORKS バランスの取れた色彩感覚と暮らしやすさを考えた動線計画で、女性からも人気のあるデザイナー。休日は料理とキャンプをするのが定番です。 CREATOR’s STORY|片山 飛翔 |
|---|
コンクリート打ちっぱなしの建物は、クールでスタイリッシュな見た目が人気で、近年では店舗やオフィスだけでなく、新築の家やリフォームを検討する際にも選択肢の一つとして注目されています。しかし、リフォームを検討する際には、そのメリットだけでなく、費用面や機能面でのデメリット、そしてそれに対する適切な対策を事前に理解しておくことが重要です。本記事では、コンクリート打ちっぱなしの魅力と課題を掘り下げ、快適な住まいを実現するための具体的な情報を提供します。
目次
コンクリート打ちっぱなしとは

コンクリート打ちっぱなしとは、RC(鉄筋コンクリート)造やSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造の建物において、コンクリートの素材感をそのまま活かして仕上げる建築手法を指します。
通常、コンクリートは型枠を外した後に塗装やタイルなどで表面を仕上げますが、この工程を省き、コンクリートの地肌をそのまま見せるのが特徴。この仕上げは、デザイン性の高さからデザイナーズマンションや一戸建ての家でよく採用されています。特に、戦後の日本でコンクリートの建物が増加した際、当初は公共建築物に用いられ、その当時の杉板型枠の模様を活かすデザインが主流でした。
無機質でありながらも、その素材感が独特な美しさを生み出し、新築の家を建てる際やリノベーションで個性を求める際に選択される人気のデザインです。
建物の仕上げ方法
コンクリート打ちっぱなしは、建物の構造体であるコンクリートの表面に、塗装やタイル、壁紙などの仕上げ材を施さずに、コンクリートの地肌をそのまま見せる仕上げ方法です。RC(鉄筋コンクリート)造やSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造といった、鉄筋を組んだ型枠にコンクリートを流し込んで固める構造の建物で採用されます。型枠には通常、打ち放し用の合板が使用されますが、杉板を用いることで木目をコンクリートに転写させるといった手法も存在します。
このように型枠を外した状態のコンクリートをそのまま活かすことで、無機質でスタイリッシュな雰囲気を演出できるのが特徴です。一般的な建物では、コンクリートの躯体に外壁であれば塗装やタイル、内壁であれば壁紙や塗装などで仕上げを施しますが、コンクリート打ちっぱなしではこれらの工程を省略。しかし、外壁の場合は耐水性を向上させるために、通常は撥水剤の塗布が行われます。
外壁と内壁への適用
コンクリート打ちっぱなしは、建物の外壁と内壁の両方に適用可能です。外壁に採用する場合、クールで都会的な外観となり、シンプルなデザインでありながらスタイリッシュな印象を与えます。しかし、外壁をコンクリート打ちっぱなしにする場合、断熱対策が重要となります。コンクリートの躯体の外側に断熱材を施工する外断熱工法では、外壁はタイル貼りなどになるため、コンクリート打ちっぱなしの外観にはなりません。
一方、躯体の内側に断熱材を施工する内断熱工法であれば、外壁をコンクリート打ちっぱなしにすることが可能です。この場合、内壁側は断熱材の上にプラスターボードを貼り、壁紙などで仕上げます。
内壁にコンクリート打ちっぱなしを適用する場合、室内に無機質で洗練された雰囲気を演出し、インテリアコーディネートの幅を広げます。天井や壁に仕上げ材を使用しないことで、空間を広く見せる効果も期待できます。特に、木材やファブリック、観葉植物などと組み合わせることで、温かみのあるおしゃれな室内空間を創造することも可能です。マンション、戸建て、店舗、オフィス、カフェ、ガレージ、平屋など、さまざまな建築物や空間で取り入れられています。
例えば、カフェではヴィンテージ感のある雰囲気を演出したり、オフィスではインダストリアルな空間をデザインしたりする際に活用されます。壁紙やクロスでは得られない、コンクリートならではの質感は、洗練された内装デザインを求める人に選ばれています。
ただし、内壁を打ちっぱなしにする場合は、断熱材を内側に施工することが難しいため、外断熱工法で建物の外側に断熱材を施工する必要があります。内装の一部にのみコンクリート打ちっぱなしを取り入れることも可能で、例えば一面の壁だけを打ちっぱなしにするなど、デザインの自由度が高いのも特徴です。
コンクリート打ちっぱなしのメリット

ここからはコンクリート打ちっぱなしのメリットとデメリットをそれぞれ見ていきいましょう。まずはメリットからご紹介します。
デザイン性
コンクリート打ちっぱなしの最大のメリットは、その高いデザイン性です。無機質でクールなグレーの色合いが、シンプルでありながらも洗練された都会的な印象を与え、スタイリッシュでおしゃれな空間を演出します。コンクリートの質感は、現代的なモダンテイストはもちろん、ヴィンテージ、ナチュラル、ラグジュアリー、インダストリアルなど、様々なインテリアテイストと相性が良く、加えるインテリアによって空間の雰囲気を自在に変えることが可能。
例えば、ウッド調の家具や観葉植物を取り入れることで、無機質な空間に温かみやアクセントを加えることができます。また、ガラスや金属といった無機質な素材や、直線的でシンプルなデザインの家具ともよく馴染み、デザイナーズ家具との相性も抜群。
空間の広さ
コンクリート打ちっぱなしの建物は、柱を最小限に抑えた空間設計が可能です。これは、RC造やSRC造といった鉄筋コンクリート構造が、木造や鉄骨造に比べて柱と柱の間のスパン(距離)を長く取れる特性を持つためです。その結果、間仕切り壁をあまり設けることなく、開放的で広々とした大空間を実現できます。
天井も仕上げ材による厚みがないため、高さが出て開放感のある部屋が多くなります。このような柱の少ない広い空間は、家具のレイアウトの自由度を高め、例えば開放的なLDK(リビング・ダイニング・キッチン)にするなど、住宅のデザインの自由度も向上させます。
また、天井のハリがないため、家具の配置がしやすくなるというメリットもあります。玄関からリビング、ダイニング、キッチンへと視線が広がるような、つながりのある間取りも実現しやすいため、家族間のコミュニケーションを円滑にする効果も期待できます。
防音性
コンクリート打ちっぱなしの建物は、高い防音性を備えていることがメリットの一つです。コンクリートは原料に岩石を用いており、重量があり密度が非常に高いため、音が伝わりにくく、優れた遮音効果を発揮します。
特にRC鉄筋コンクリート造やSRC鉄骨鉄筋コンクリート造といった、コンクリートを打ち込んで施工する構造は、非常に高い防音効果があると言われています。これにより、外部からの騒音を効果的に遮断し、静寂な室内環境を保つことが可能。
例えば、都市部に住んでいて外の騒音が気になる方や、隣の部屋の生活音が気になる方にとっては、静かで快適な生活を送れるでしょう。また、室内の音も外部に漏れにくいため、楽器の演奏やホームシアターなど、音が出る趣味を持つ方や、小さなお子さんがいる家庭にも適しています。
ただし、物件によってコンクリートの重度や密度、床スラブの厚みによって遮音性は異なるため、内見時に確認することが重要です。また、配管や電気配線などをコンクリートの外に露出させる設計の場合、その空間が音の通り道となり、隣人の生活音が聞こえてしまう可能性もあるため、注意が必要です。一般的なコンクリート壁厚さ150mm程度の場合、約50~60dBの遮音性能が期待できるとされています。
耐震性と耐火性
コンクリート打ちっぱなしの建物は、構造上、高い耐震性と耐火性を兼ね備えています。耐震性に関しては、コンクリート打ちっぱなしはRC造やSRC造といった構造でできており、これらは引っ張りに強い鉄筋と圧縮に強いコンクリートで構成されているため、非常に高い強度を誇ります。そのため、木造住宅と比較して耐震性が高く、地震に強い建物として知られています。特にSRC造は鉄骨を内蔵しているため、耐震性能がさらに高まります。
耐火性については、コンクリートは不燃材料であり、非常に火に強い素材です。例えば、火災時の炎は1000度まで上昇しますが、RC造のコンクリートは1,000度の火に2時間さらされても燃えません。一方、木造は火災の際に260度で発火し、1,000度に達する前に倒壊する可能性があります。この高い耐火性により、建物自体が燃えにくいだけでなく、周囲の建物への延焼リスクも低減します。
また、火災に強いことから「耐火建築物」となり、火災保険料が安くなるというメリットもあります。これらの特性は、建物の耐用年数にも影響を与え、RC造・SRC造のコンクリート打ちっぱなしの建物は、木造の家に比べて耐久性が高く、耐用年数も長くなる傾向にあります。災害に強く、長期的な安全性と経済性を考慮すると、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
耐久性
コンクリート打ちっぱなしの建物は、その素材の特性上、高い耐久性を持っています。RC(鉄筋コンクリート)造やSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造という強固な構造によって建てられており、木造住宅と比較して耐用年数が長い傾向にあります。コンクリートは非常に頑丈な素材であり、適切に施工されれば、経年による大きな劣化や修繕の頻度を抑えることが可能です。
しかし、コンクリート打ちっぱなしは、塗装やタイルなどで表面が覆われていないため、雨水や紫外線などの外部環境の影響を直接受けやすく、経年劣化の進行が比較的早いという側面もあります。具体的には、雨染みやひび割れ、表面のザラつき、カビの発生などが目立ちやすいといったデメリットも挙げられます。これらの劣化症状は、美観を損なうだけでなく、放置すると建物の性能低下につながる可能性もあります。
そのため、打ちっぱなしコンクリートの美観と機能を長く保つためには、定期的なメンテナンスが非常に重要になります。定期的な補修や塗装を行うことで、これらの劣化を未然に防ぎ、建物の寿命を延ばし、美しい状態を維持することができるのです。撥水剤の塗布や、ひび割れ補修、清掃などの適切な修繕を施すことで、コンクリート打ちっぱなしの建物の耐久性を最大限に引き出すことが可能となります。
コンクリート打ちっぱなしのデメリット
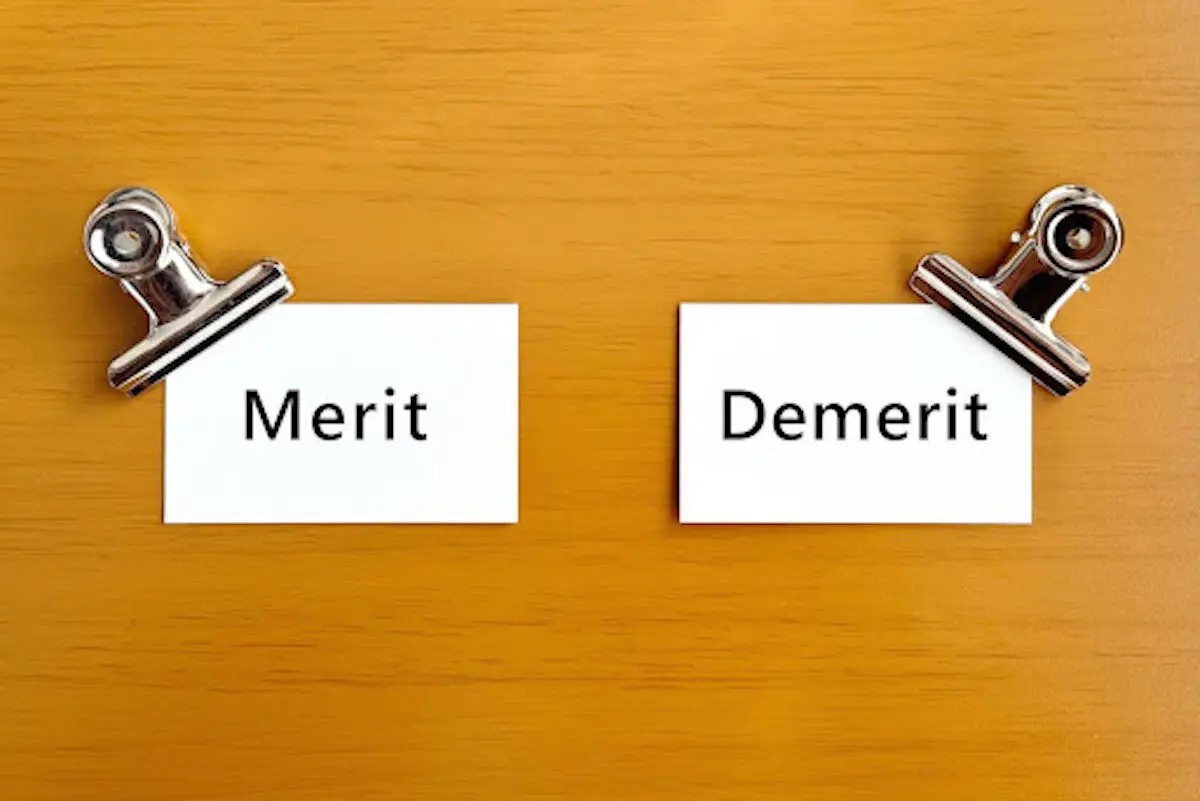
コンクリート打ちっぱなしの建物は、その洗練されたデザインで人気を集める一方で、いくつかのデメリットも存在します。一つずつ確認しておきましょう。
外気の影響
コンクリート打ちっぱなしの建物は、外気の影響を受けやすいというデメリットがあります。これは、コンクリートが熱伝導率の高い素材であるため、外の温度変化を室内に伝えやすい性質を持っているためです。その結果、夏は暑く、冬は寒いと感じやすい傾向にあります。特に、外壁と内壁の両方が打ちっぱなしになっている物件では、外壁と内壁の間に断熱材が入っていないケースもあり、より一層外気の影響を受けやすくなります。
また、コンクリートは熱を蓄積しやすい特性も持っているため、夏は一度室内に熱がこもると冷えにくく、冬は温まりにくいという問題が生じます。これにより、冷暖房の効率が悪くなり、光熱費がかさむ可能性が高まります。快適な室内環境を保つためには、適切な断熱対策が不可欠です。
結露とカビ
コンクリート打ちっぱなしの建物では、結露とカビが発生しやすいというデメリットがあります。コンクリートは吸水性が高く、内部に湿気を溜め込みやすい性質を持つため、室内の湿度が上昇しやすいのです。特に、外気と室内の温度差が大きくなる冬場は結露が発生しやすく、その水分がカビの繁殖を促進する原因となります。
新築や築浅のコンクリート打ちっぱなし物件では、コンクリート内部の水分が完全に乾燥するまでに数年かかることもあり、湿気がこもりやすい傾向があります。
また、コンクリートは高気密であるため、十分に換気ができないと湿気が室内に滞留し、カビが生えやすくなります。カビは健康に悪影響を及ぼすだけでなく、壁の黒ずみとして残り、美観を損ねる原因にもなります。結露やカビの発生を防ぐためには、適切な湿気対策が不可欠です。こまめな換気、除湿器や除湿剤の活用、家具と壁の間に隙間を設けるなどの対策が有効です。
また、カビは気温が20℃~35℃、湿度が70%以上で繁殖しやすくなるため、室内の温度と湿度を適切に管理することも重要です。
汚れの付着
コンクリート打ちっぱなしは、その表面に塗装や壁紙などの仕上げ材が施されていないため、汚れが付着しやすいというデメリットがあります。特に、外壁は雨水や紫外線、排気ガスなどの影響を直接受けるため、シミや変色、黒ずみなどが起きやすい状態です。コンクリートの表面は、これらの汚れが目立ちやすく、美観を損なう原因となります。
また、コンクリートは水分を吸収しやすい性質を持っているため、水滴や液体の汚れがシミになりやすいという特徴もあります。壁面に凹凸がある場合は、埃やカビも付着しやすく、一度ついてしまうと拭き取るのが難しい場合もあります。
これらの汚れを防ぎ、美しい状態を長く保つためには、定期的なメンテナンスが重要です。
施工品質
コンクリート打ちっぱなしの建物は、施工品質が非常に重要となるというデメリットがあります。コンクリート打ちっぱなしは、型枠を外したそのままのコンクリートの表面を仕上げとするため、わずかな施工不良や不具合がそのまま外観に現れてしまいます。
例えば、ひび割れやジャンカ(コンクリートの打設不良による隙間)、色ムラ、コールドジョイント(コンクリートの継ぎ目)などが生じると、それが直接的な瑕疵となり、建物の美観を損ねるだけでなく、耐久性にも影響を及ぼす可能性があります。ひび割れが放置されると、そこから雨水が浸入し、雨漏りの原因となったり、内部の鉄筋が錆びて建物の構造自体を傷めることにもつながります。
また、コンクリートは乾燥収縮によって微細なひび割れが発生しやすい性質も持っています。そのため、コンクリート打ちっぱなしの施工には、一般的な仕上げを行う建物よりも高い技術と経験が求められます。
建築費用
コンクリート打ちっぱなしの建物は、一般的な木造住宅や鉄骨造の住宅と比較して、建築費用が高い傾向にあることがデメリットとして挙げられます。具体的な費用の目安としては、木造住宅の坪単価が平均60万円前後であるのに対し、コンクリート造は安くても坪単価100万円程度から、場合によっては坪単価180万円(工事費/延べ面積)以上かかることもあります。
建築費用が高くなる主な理由はいくつかあります。まず、コンクリート打ちっぱなしの施工には、現場で型枠を組み、そこにコンクリートを流し込み、鉄筋を組むといった、より専門的な技術と手間のかかる工程が必要となります。型枠の組み立てやコンクリートの打設には高い精度が求められるため、熟練の職人による作業が不可欠であり、その人件費も高くなる要因の一つ。特に、型枠を組み立てる型枠大工はなり手が不足しているのが現状であり、これが建築費に影響を与えています。
また、コンクリートの材料費や、木造住宅よりも工期が長くなる傾向があるため、その人件費や管理費用も増加します。加えて、コンクリート打ちっぱなしの建物は、断熱性や気密性を高めるための追加の施工が必要となる場合があり、これもコストアップにつながります。
予算が限られている場合は、建物の構造の一部にのみコンクリート打ちっぱなしを取り入れた「混構造」(例えば1階はコンクリート打ちっぱなし、2階以上は木造など)を検討することで、コストを抑えることも可能です。
コンクリート打ちっぱなしの対策

これまで確認してきたデメリットの個別の対策をチェックしておきましょう。
断熱施工の確認
コンクリート打ちっぱなしの建物は、コンクリートの熱伝導率が高い特性から、夏は暑く冬は寒いという外気の影響を受けやすいデメリットがあります。この問題を解決し、快適な室内環境を保つためには、適切な断熱施工が不可欠です。
断熱施工には主に「外断熱」と「内断熱」の2つの方法があります。
外断熱工法は、コンクリートの躯体の外側に断熱材を施工する方法です。この方法では、コンクリート自体が外気の影響を受けにくくなるため、コンクリートの蓄熱性を活かしつつ、室内の温度変化を抑える効果が期待できます。しかし、外壁をコンクリート打ちっぱなしにしたい場合、外断熱にすると打ちっぱなしの外観にはならないというデメリットがあります。
一方、内断熱工法は、コンクリートの躯体の内側に断熱材を施工する方法です。外壁をコンクリート打ちっぱなしのままにしたい場合は、内断熱を選択することになります。この場合、内壁側は断熱材を施工した上でプラスターボードを貼り、壁紙などで仕上げるのが一般的です。
どちらの断熱工法を選ぶかは、コンクリート打ちっぱなしにしたい場所(外壁か内壁か)や、デザインの好みによって異なります。理想的なコンクリート打ちっぱなしの住まいにするためには、「外気に接する壁」の断熱が必須であり、断熱材と気密性のあるサッシが必要になります。建築を検討する際は、専門家と相談し、建物の立地や気候条件に合わせた最適な断熱施工を確認することが重要です。
また、既存のコンクリート打ちっぱなし物件に住む場合でも、窓に断熱性の高いカーテンをつけたり、壁に断熱性のあるクッションシートを貼ったりするなどの対策で、寒さ対策が可能です。
適切な換気
コンクリート打ちっぱなしの建物は、気密性が高く、湿気がこもりやすいという特性を持っています。これは、コンクリートが吸水性が高く、内部に湿気を溜め込みやすい性質を持つため、結露やカビが発生しやすい原因となります。
この湿気の問題を軽減し、カビの発生を防ぐためには、適切な換気が非常に重要。定期的に窓を開けて外の空気を取り入れることで、室内の湿度を下げ、通風を促すことができます。特に、料理やお風呂など水蒸気が多く発生する場所では、換気扇を積極的に使用し、湿気を外部に排出する工夫が必要です。換気を行う際には、対角線上にある窓を開けることで、より効果的な空気の流れを作り出すことが可能です。
また、換気が難しい梅雨時期や冬場などは、除湿機やエアコンの除湿機能を活用することも有効な湿気対策となります。クローゼットなどの収納スペースには、置き型タイプの除湿剤やシリカゲルシートを置くのも効果的です。家具を壁から5cm程度離して配置することで、壁と家具の間に空気の通り道を作り、結露やカビの発生を抑制できますよ。
湿気対策
コンクリート打ちっぱなしの建物では、コンクリートが吸水性が高く湿気をため込みやすい性質を持つため、結露やカビが発生しやすいという課題があります。快適な住環境を保ち、健康被害や建物の劣化を防ぐためには、徹底した湿気対策が不可欠です。
まず、最も基本的な対策として「こまめな換気」が挙げられます。窓を開けて部屋の空気を入れ替えたり、換気扇を回したりすることで、室内の湿気を効率的に排出できます。特に、水蒸気が多く発生するキッチンや浴室は、換気を怠らないようにしましょう。対角線上に窓を開けることで、より効果的な通風が期待できます。
次に、機械による湿度管理も有効です。除湿機やエアコンの除湿機能を活用することで、換気だけでは取りきれない室内の湿気を除去し、カビの発生を防ぐことができます。特に梅雨時期など湿度が高い季節や、暖房を使用して室内外の温度差が大きくなる冬場は、積極的に使用することが推奨されます。
また、家具の配置にも工夫が必要です。家具と壁が密着していると風通しが悪くなり、結露が発生しやすいため、家具を壁から5cm程度離して設置することで、空気の通り道を作り、結露やカビの発生を抑制できます。クローゼットなどの収納スペースには、置き型タイプの除湿剤や、吸湿性と消臭効果に優れたシリカゲルシートを活用するのも良いでしょう。新築や築浅の物件では、コンクリート内部の水分が完全に乾燥するまでに数年かかることがあるため、特に注意が必要です。
コンクリート打ちっぱなしのメンテナンスと費用

コンクリート打ちっぱなしの建物は、その独特な美しさを維持するために定期的なメンテナンスが不可欠です。適切なメンテナンスを行うことで、建物の劣化を防ぎ、長期間にわたってその魅力を保つことができます。
メンテナンスにはいくつかの方法があり、それぞれ費用や期待できる効果、メンテナンス周期が異なります。ここでは、コンクリート打ちっぱなしのメンテナンスの必要性、周期、そして具体的な方法とそれに伴う費用について詳しく解説します。
メンテナンスの必要性
コンクリート打ちっぱなしの建物には、定期的なメンテナンスが不可欠です。これは、コンクリートがその素材の特性上、塗装やタイルなどの仕上げ材で表面が覆われていないため、雨水や紫外線、風といった外部環境の影響を直接受けやすく、経年劣化の進行が比較的早いためです。
具体的な劣化症状としては、雨水がコンクリートに染み込んでできる雨染みや、微細なひび割れ、表面のザラつき、カビやコケの発生、そして紫外線による色あせなどが挙げられます。これらの劣化は、建物の美観を損ねるだけでなく、放置すると様々な問題を引き起こす可能性があります。例えば、ひび割れは雨水の浸入経路となり、雨漏りや内部の鉄筋の腐食につながり、建物の構造的な強度を低下させる原因となります。
また、コンクリートは吸水性が高いため、湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい環境になり、これは健康被害にもつながることがあります。こうした劣化を防ぎ、建物の耐用年数を長く保つためには、定期的な補修や表面保護が必要です。定期的なメンテナンスを行うことで、初期の段階で劣化を発見し、小さな補修で済ませることができ、結果的に大規模な修繕を避け、長期的なコストを抑えることにもつながります。
メンテナンスの周期
コンクリート打ちっぱなしの建物は、その美しい状態を維持するために、定期的なメンテナンスが重要です。一般的に、新築時(施工後)から約10年くらいで、雨染みやひび割れ、カビなどの劣化症状が見られるようになることが多いとされています。そのため、打ちっぱなしコンクリートの外壁塗装やその他のメンテナンスの目安としては、新築時(施工後)からおおよそ10年前後が推奨されています。
しかし、理想的な塗装周期は6~7年とする意見もあり、劣化症状や使用する塗料の種類によってもメンテナンスのタイミングは異なります。例えば、新築時に撥水剤が塗布されている場合でも、その耐久年数は2~7年程度と短いため、その効果が切れる前に再塗布を検討する必要があります。弾性塗料やクリア塗装、カラークリヤー工法など、選択するメンテナンス方法によっても耐用年数やメンテナンス周期は変わってきます。
より正確なメンテナンス時期を見極めるためには、打ちっぱなしコンクリート外壁に生じている実際の劣化症状を確認することが重要です。シミ、変色、ひび割れ、カビの発生など、目に見える変化があった場合は、早めに専門業者に診断してもらうことをおすすめします。
メンテナンス方法と費用
コンクリート打ちっぱなしの建物は、その美観と耐久性を維持するために様々なメンテナンス方法があり、それぞれに費用が異なります。主なメンテナンス方法と費用の目安は以下の通りです。
撥水剤の塗布
撥水剤の塗布は、コンクリート打ちっぱなしの新築時にも一般的に行われるメンテナンス方法の一つです。無色透明な塗料であるため、コンクリート本来の質感や風合いを損なうことなく、表面に撥水性を持たせて防水効果を高めます。これにより、雨水がコンクリートに染み込むのを防ぎ、雨染みや汚れの付着を抑制する効果が期待できます。ただし、シミなどをすでにカバーすることはできないため、美観が損なわれている状態を新築時のように戻すのには不向きです。
撥水剤の耐久年数は2~7年程度と比較的に短いため、メンテナンスの頻度が高くなる傾向があります。費用は1平方メートルあたり1,500円前後が目安とされています。定期的な再塗布によって、コンクリートの劣化を防ぎ、美観を長く保つことが可能ですよ。
弾性塗料
弾性塗料は、コンクリート打ちっぱなしのメンテナンスにおいて、ひび割れ対策に有効な塗料です。弾性塗料は、塗膜がゴムのように伸縮する特性を持っているため、コンクリートの収縮や微細なひび割れの発生に対応し、追従することで、ひび割れを抑制したり、既存のひび割れからの水の浸入を防ぐ効果があります。
この塗料を使用することで、コンクリートの表面を保護し、雨水による劣化や汚れの付着を防ぎながら、建物の耐久性を高めることができます。弾性塗料を塗装した場合の費用は、1平方メートルあたり3,000円から5,000円程度が目安とされていますが、使用する塗料の種類や施工の状況によって費用は変動する可能性があります。耐用年数は比較的長く、建物の保護と美観維持に貢献します。
カラークリヤー工法
カラークリヤー工法は、コンクリート打ちっぱなしの外壁に、半透明で色付きの塗料を塗装するメンテナンス方法です。この工法では、クリア塗装のように完全に透明ではなく、白色やグレーなどのカラーラインナップがあるため、コンクリートの質感を活かしつつ、薄く色をつけることで、より均一な仕上がりにしたり、コンクリートの風合いを調整したりすることが可能です。既存のコンクリートの汚れや色ムラが気になる場合に、それらをカバーしながら、打ちっぱなしの雰囲気を保ちたい場合に適しています。
また、コンクリートの表面を保護し、汚れや水分の浸透を防ぐ効果も期待できます。費用は1平方メートルあたり4,000円から7,000円程度が目安とされており、使用する塗料や施工面積、足場の設置費用などによって変動します。コンクリート打ちっぱなしの独特な表情を保ちながら、美観を向上させたい場合に有効な選択肢となります。
ファンデーション工法
ファンデーション工法は、コンクリート打ちっぱなしの表面に生じた、ひび割れやジャンカ、色ムラといった劣化症状を補修し、まるでファンデーションを塗るようにコンクリートの美しい状態を再現する工法です。この工法は、劣化した部分を部分的に補修するだけでなく、全体的にコンクリートの風合いを整え、新築時のように均一で美しい状態に戻すことを目的としています。
具体的には、ひび割れの補修、欠損部の充填、表面の研磨などを行い、その上から特殊な塗料やコーティング剤を塗布することで、コンクリートの質感や色合いを忠実に再現します。この際、コンクリートの持つ独特の表情や、ピーコン穴と呼ばれる型枠の跡なども考慮して仕上げられるため、非常に自然な仕上がりが期待できます。ファンデーション工法は、経年劣化によって美観が損なわれたコンクリート打ちっぱなしの建物のリノベーションや大規模な修繕に特に適しています。
費用は、劣化状況や施工面積によって異なりますが、一般的な費用は1平方メートルあたり7,000円から15,000円程度が目安とされています。この工法は、コンクリート打ちっぱなしの建物の価値を再生し、長期的に美観を維持するための有効な補修手段となります。
コンクリート打ちっぱなしのおしゃれな事例
マンションの事例
<50.5㎡>着想はホテルの客室。趣味とこだわりを詰め込んだ大人のワンルーム【大阪市城東区】
オールステンレスのキッチンと相性がいいコンクリート剥き出しの壁。クロスで仕上げるよりも雰囲気がでます。
<51.9㎡>天井が主役。ミニマリズムな賃貸リノベ【大阪市淀川区】

今回は天井をあえて作らずコンクリート露し仕上げを提案しました。
コンクリートは冷たいイメージを与えますが、自然光が当たることや木目とのバランスによって逆に柔らかく見せることもできます。また、天井高を確保できるため空間が広がることでより開放的でダイナミックな印象を与えます。
コンクリート打ちっぱなしは断熱施工とメンテナンスが鍵!
コンクリート打ちっぱなしの建物は、無機質で洗練された美しさと、防音性・耐震性・耐火性・長寿命といった機能面の優位性が魅力です。
一方で、夏の暑さや冬の寒さ、結露、施工費用の高さといった課題もあります。これらは断熱施工や換気、表面保護材の活用などで対策が可能。美観と快適性を維持するには定期的なメンテナンスも大切です。
リフォーム・リノベーションを検討する際は、メリット・デメリット・対策・費用を総合的に理解し、実績ある専門業者と相談しながら、理想の住まいを実現しましょう。